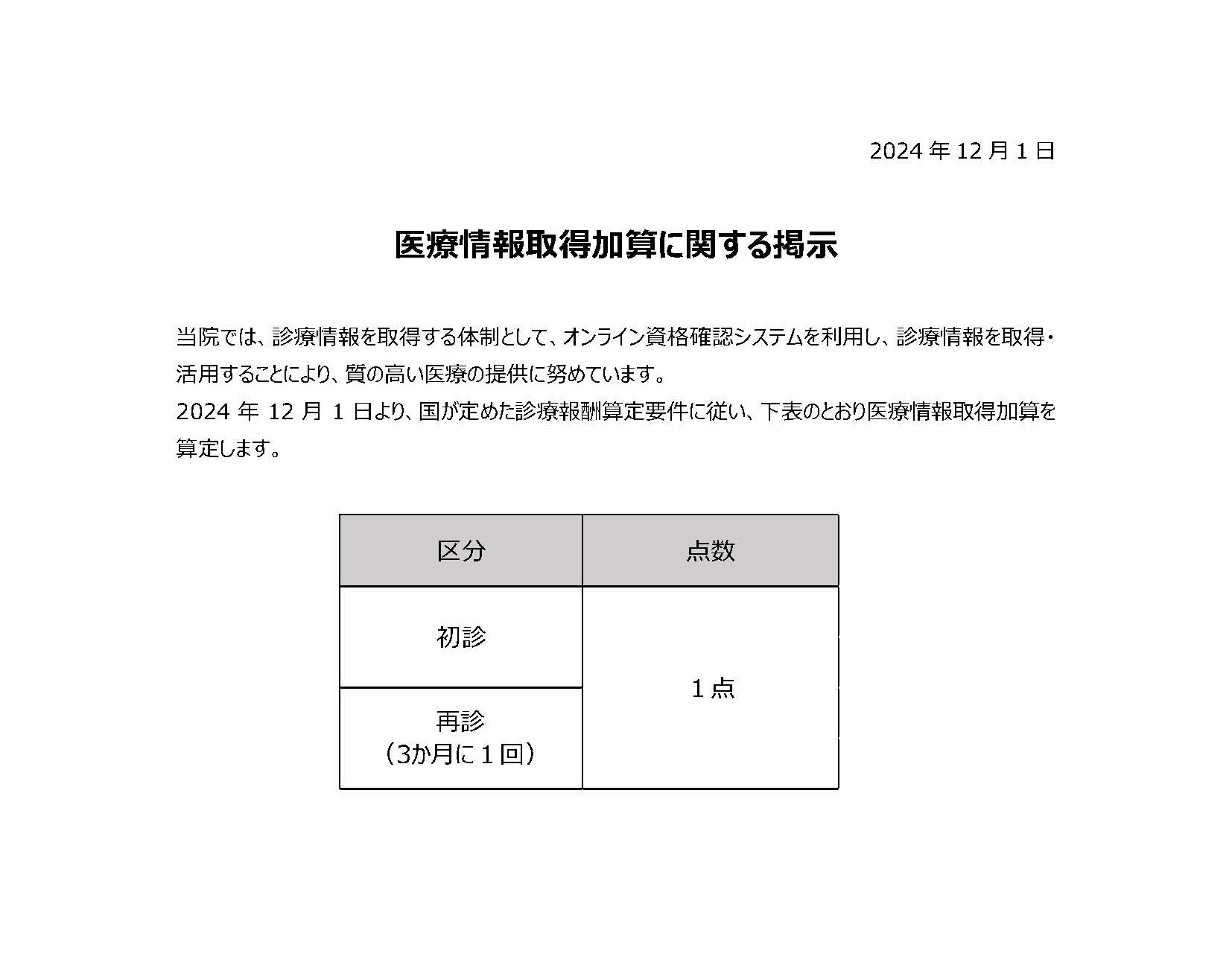- HOME
- お知らせ
お知らせ
フルミストとは

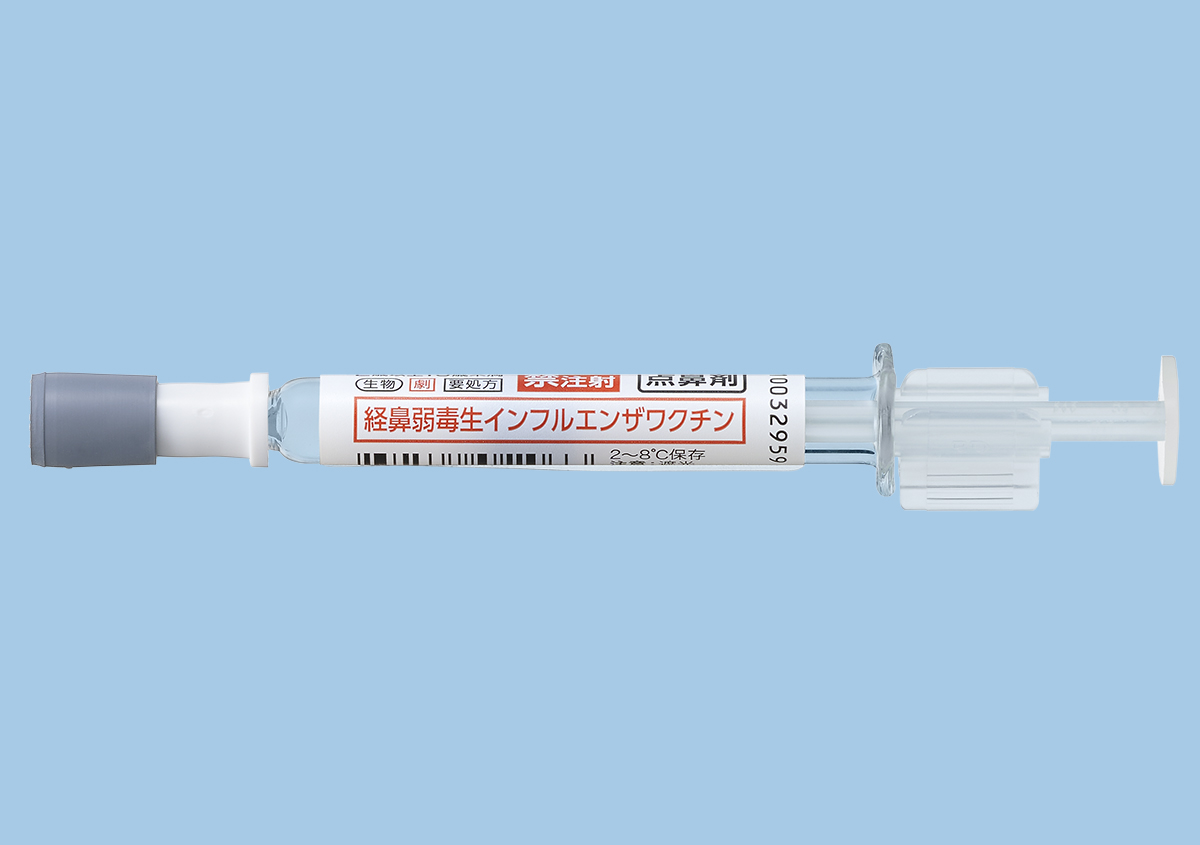
フルミストとは
フルミストとは従来のインフルエンザワクチンとは異なり、注射器を用いず鼻の中に噴霧するタイプのワクチンです。
ウイルスの活性を低下させたインフルエンザウイルスを鼻腔内に噴霧することで、体の中でインフルエンザウイルスに感染したときと類似した環境を作ることでインフルエンザウイルスに対する免疫を誘導する働きがあります。
アメリカやヨーロッパの国々で承認されていましたが日本では未承認のワクチンでした。しかし、2024年度より日本でも承認が使用されました。
そのため当院でもフルミストを採用いたしました。
特徴
- 鼻から噴霧するため、注射による痛みや怖さがない
- 小児による有効性が高い
- 効果は1シーズンで、従来のワクチンよりも効果の持続時間が長い
- 鼻粘膜にも免疫を誘導するため、ワクチン株が実際の流行株と違ったとしても発症を軽減することが期待できる
フルミストの対象
2歳〜19歳未満のお子さん
接種回数・方法
1回
※専用の接種器具を用いて、左右の鼻の中に0.1mlずつ、計0.2ml噴霧します。
接種費用
1回8,500円(足立区では1回6,000円の助成金がでます。)
副反応
フルミストは、弱毒化した生ワクチンを鼻に噴霧することから、鼻水、鼻づまり、咳、頭痛などの症状が報告されています。
接種日当日に鼻水や鼻づまりが強い方は、フルミストの効果が低下する可能性があるため、この場合は従来のインフルエンザワクチンの接種をおすすめいたします。
他のワクチンと同様に、極めてまれですがアナフィラキシーショック等を起こす可能性もあります。
また、フルミスト接種後2か月以内の妊娠は禁止されています。
発熱外来受付時間

発熱外来受付時間 午前は12時まで 午後は5時15分までに来院お願いいたします。
感染症の検査(経鼻による抗原検査)に時間を要する場合があるために時間を過ぎてしまいますとお断りする場合がございますのでご理解の程お願いいたします。
新型コロナウイルス感染症について


令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は2類から5類感染症になりました。
外出などの制限が無くなります。
令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
- 外出を控えることが推奨される期間
特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目 (※1)として5日間は外出を控えること(※2)、かつ、5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。
(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、
症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。 - 周りの方への配慮
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。
医療機関の受診について
熱っぽい、咳が出るような症状があり、検査キットで陽性となった高齢の方、症状が重い方、薬を飲んでも症状がおさまらない方は、受診の前に電話をしてから、かかりつけ医や近所の医療機関を受診しましょう。発熱診療等医療機関に加え、幅広い医療機関で受診可能となります。公共交通機関で受診する際はマスクを着用しましょう。また、検査キット陽性となった若い方・症状が軽い方については、陽性者登録窓口は終了となります。自宅で療養しましょう。
帯状疱疹が若年者に急増中!

2014年に小児の定期接種化が始まり小児の水痘罹患が減りました。
子育て世代の20~40歳代の人たちが水痘ウイルスに暴露される機会が減ってしまい、年間発症率が増えています。
若年の方は早期発見のために早めに病院受診をして抗ウイルス薬を使い帯状疱疹後神経痛を残さないようにすることが大切だと考えます。
また50歳以上の方は2020年1月から新たなワクチンが選択肢に加わりました。
子宮頸がんワクチン

シルガ-ド9(令和5年4月からの新しい子宮頸がんワクチン9価HPVワクチン)
足立区では令和5年4月から接種が始まる新しい子宮頸がんワクチンです。
(ヒトパピロ-マウイルスワクチン)
従来の子宮頸がんワクチン・ガーダシル®(4価HPVワクチン)に含まれるHPV6/11/16/18型に加え、HPV31/33/45/52/58型の5価の型を加え9価となったワクチンです。これにより幅広く予防効果を期待できるようになりました。

用法用量
9歳以上の女性に、1回0.5 mLを合計3回、筋肉内に注射する。通常、2回目は初回接種の2ヵ月後、3回目は6ヵ月後に同様の用法で接種する。
9歳以上15歳未満の女性は、初回接種から6~12ヵ月の間隔を置いた合計2回の接種とすることができる。
キャッチアップ接種について(3回接種無料)
令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間にわたり、キャッチアップ接種として公費での接種を実施しています。平成9年度生まれ〜平成17年度生まれ(誕生日が1997年4月2日〜2006年4月1日)の女性や過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない方です。
当初は3回接種を2025年3月末までに終える必要がありましたが、1回でも接種すれば残り2回を翌年度内に無料で接種可能になります。

接種間隔
9歳以上の女性に合計3回の接種をする場合、1年以内に3回の接種を終了することが望ましい。なお、本剤の2回目及び3回目の接種が初回接種の2ヵ月後及び6ヵ月後にできない場合、2回目接種は初回接種から少なくとも1ヵ月以上、3回目接種は2回目接種から少なくとも3ヵ月以上間隔を置いて実施すること。
9歳以上15歳未満の女性に合計2回の接種をする場合、13ヵ月後までに接種することが望ましい。なお、本剤の2回目の接種を初回接種から6ヵ月以上間隔を置いて実施できない場合、2回目の接種は初回接種から少なくとも5ヵ月以上間隔を置いて実施すること。
2回目の接種が初回接種から5ヵ月後未満であった場合、3回目の接種を実施すること。この場合、3回目の接種は2回目の接種から少なくとも3ヵ月以上間隔を置いて実施すること。

副反応
注射部位では疼痛、腫脹、紅斑、そう痒感、内出血、腫瘤、出血が、全身性の副反応としては頭痛、発熱、悪心、浮動性めまい、疲労、下痢、口腔咽頭痛、筋肉痛が報告されています。
予防効果
3回接種法
9~15歳の女性を対象にした臨床試験(002-20試験)では10年間、16~26歳の女性を対象にした臨床試験(001試験)では少なくとも5年の抗体反応の持続性が確認されています。
2回接種法
9~14歳の女性を対象にした臨床試験(010試験)では3年の抗体反応の持続性が確認されています。